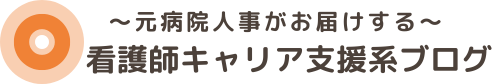転職を決意して、いざ情報収集を始めてみると、膨大な求人広告を前に
- 「なかなか候補先を絞れない…」
- 「もう面倒!」
となって、転職活動を先送りにしている…
そんな人も少なくないのではないでしょうか?
やみくもに情報だけを集めてみても、目移りばかりしてなかなか職場選びは進みません。
効率的に転職活動を進めるためには、あなたなりの確かな指標を持つことがとても大切です。
本記事では、看護師がやめた方がいい職場の特徴を紹介し、今後の職場選びのポイントについても解説します。
この記事を読んで、今後のキャリアプランや転職活動の参考にしていただけるとうれしいです。
看護師の離職率は高いのか?

看護師が職場選びで失敗しないために、まず前提として押さえておきたいのは、就職でうまくいかなかった看護師たちが残してくれた生の声や客観的な数字です。
- なぜ、看護師たちは職場を去ってしまったのか?
- どれ位の看護師たちが、職場を去っていったのか?
はじめに、看護師の離職率の現状について確認していきたいと思います。
看護師の離職率を知る
辛い看護実習を乗り越え、国家試験にも合格し、晴れて希望の医療機関に入職!
…したのも束の間、職場を後にしてしまう新人看護師たち。実は10人に1人の割合でいることがわかっています。
学生時代に想い描いていた看護師の理想の姿と、実際に働いてみて感じた現実とのギャップに戸惑いを感じている人はとても多いのではないでしょうか。
日本看護協会が行った「2024年 病院看護実態調査」によると、看護師の離職率は以下のとおりとなっています。
- 正規雇用看護職員離職率 11.3%(前年度:11.8%)
(最高)東京都14.2%
(最低)岩手県・山形県6.8% - 新卒採用者離職率 8.8%(前年度:10.2%)
(最高)香川県15.2%
(最低)富山県2.8% - 既卒採用者離職率 16.1%(前年度:16.6%)
(最高)大分県22.4%
(最低)秋田県7.3%
引用:日本看護協会 2024年病院看護実態調査報告書
2023年度の正規雇用看護職員全体の離職率は11.3%でした。
そのうち新卒採用者が8.8%、既卒採用者が16.1%と、新卒と既卒で離職する割合に大きな差があることがわかります。
離職理由については後で触れますが、ライフステージの変化やキャリアアップなどの理由の他、看護師として何年か経験してからでしかわからない業務自体の過酷さがこの数字から見て取れます。
また、地域によっても離職率に大きな差があることがわかります。
2023年度の実績だけを見ると、新卒の離職率が最も高い香川県(15.2%)では、最も離職率の低い富山県(2.8%)に比べて5倍以上の割合で新卒看護師が離職していたことが数字で示されています。
労働者全体の離職率は?
看護職員の離職率がわかったところで、次に労働者全体(パート除く一般労働者)の離職率を確認したいと思います。
- 令和6年(2024年)離職率 11.5%
- 令和5年(2023年)離職率 12.1%
- 令和4年(2022年)離職率 11.9%
- 令和3年(2021年)離職率 11.1%
- 令和2年(2020年)離職率 10.7%
- 令和元年(2019年)離職率 11.4%
引用:厚生労働省ホームページ「令和6年 雇用動向調査結果の概要」 kekka_gaiyo-01.pdf
2019年以降の労働者全体(パート除く一般労働者)の離職率は、上記のとおり11%前後で推移しています。
前の項でみた看護師全体の直近の離職率が11.3%なので、一般労働者とほぼ同等か、むしろ労働者全体より若干低い結果となっています。
元々看護師は、比較的入退職の激しい流動性の高い職種でしたが、このところの社会全体の人手不足を背景として、労働者全体の雇用流動化の進展があらわれた数字だと考えられます。
なぜ看護師たちは職場を去ってしまったのか?

次に、なぜ看護師たちは職場を去ってしまったのか?について考えていきたいと思います。
日本看護協会の調査と、看護師人材紹介を手がける株式会社エス・エム・エスの調査の2つを参考に、「看護管理者が考える離職理由」と「看護師本人が語る離職理由」をそれぞれ紹介したいと思います。
看護管理者が考える看護師たちの退職理由
まず、看護管理者が考える看護師たちの退職理由についてみてみましょう。
日本看護協会「2024年 病院看護実態調査 報告書」より、採用年度末までに退職した新卒採用看護師について、看護管理者が考える主な退職理由の上位5位を紹介します。
| 看護管理者が考える新卒看護師の退職理由(5つまでの複数回答) | ||
| 1位 | 健康上の理由(精神的疾患) | 52.5% |
| 2位 | 自分の看護職員としての適性への不安 | 47.4% |
| 3位 | 自分の看護実践能力への不安 | 41.6% |
| 4位 | 上司・同僚との人間関係 | 29.8% |
| 5位 | 他施設への関心・転職 | 21.8% |
続いて、退職した看護師本人が明かす退職理由についてみていきたいと思います。
看護師本人が明かす前職の退職理由
株式会社エス・エム・エスが全国の看護師18,130人を対象に行った「看護師の働き方に関する意識調査」より、
Q.前職の退職理由について、当てはまるものをすべて選択してください。
という質問に対する回答結果が、以下のとおりとなっています。
| 看護師本人が明かす前職の退職理由 | ||
| 1位 | 人間関係への不満 | 31.0% |
| 2位 | 仕事内容への不満 | 24.8% |
| 3位 | 管理職のマネジメントへの不満 | 20.3% |
| 4位 | ライフスタイルの変化(妊娠・出産) | 19.2% |
| 5位 | 給与などの待遇が悪い | 18.4% |
この調査から得られた回答は、既卒看護師を含めたものですので、一概に、看護管理者が考える新卒看護師の退職理由と同列に見ることはできないとは思いますが、両者の間に違いが見られたので参考のために紹介しました。
看護管理者視点の退職理由では、「人間関係」を理由とする回答が4番目の29.8%でしたが、看護師本人からは「人間関係への不満」という回答が最も多く(31.0%)なっています。
一方、看護管理者側で最も多く考えられていた「健康上の理由(精神的疾患)」という回答(52.5%)は、看護師本人の回答では9番目(欄外)の11.5%という低い結果でした。
このように、管理者から見た退職理由と、看護師本人が訴える退職理由に不一致がみられることからも、就業時から両者の間で働き方の意識にギャップがあったことや、コミュニケーションエラーがおきていた可能性が否定できません。
なお、看護師を辞めたいと思ったときに考えるべきこと、また、転職を考え始めたときの心の準備の仕方について、以下の2つの記事で解説していますので併せてご参考ください。
看護師がやめた方がいい職場とは

ここからは、看護師にとってやめた方がいい職場とはどのような職場なのか、考えていきたいと思います。
筆者が考える看護師がやめた方がいい職場とは、次の6つになります。
- 長時間労働が常態化している職場
- 休みが取りづらい職場
- ハラスメントが横行している職場
- 教育・研修体制が整っていない職場
- チームワークや人間関係が良好でない職場
- 患者の安全や医療の質が軽視されている職場
以下、それぞれみていきたいと思います。
1.長時間労働が常態化している職場
1-①やめた方がいい理由
長時間労働が常態化している職場は、過労によりあなたの心身の健康を害することはもとより、過労死するリスクも否定することができません。
長時間労働が慢性的に続くと、頭の働きがどうしても鈍くなりますので、業務効率は低下し、看護技術の習得も遅くなり、ますます時間内に仕事が終わらなくなります。
さらに、医療ミスのリスクが高まることから、患者の安全にも影響を及ぼす可能性があります。
日本看護協会「2024年 病院看護実態調査 報告書」によると、正規雇用看護職員の 2024年9月における1人あたりの月平均超過勤務時間は、以下のとおりとなっています。
- 20時間以上 0.8%
- 15~20 時間未満 2.3%
- 10~15 時間未満 9.8%
- 7~10 時間未満 15.4%
- 4~7 時間未満 22.5%
- 1~4 時間未満 32.1%
- 0~1 時間未満 11.5%
- 0時間 3.4%
- 無回答・不明 2.3%
- (参考値:平均5.1時間)
日本看護協会 2024年病院看護実態調査報告書 より引用し筆者まとめ
上の資料を見ると、最も多い超過勤務時間数は月に「1~4時間未満」で32.1%、2番目が「4~7時間未満」で22.5%、3番目が「7~10時間未満」で15.4%になります。
資料の数字をご覧になってどのように感じたでしょうか。恐らく、「ちょっと少ないのでは?」と感じたのではないでしょうか。
冬場と比べて患者数が落ち着く9月に調査が行われたという影響があるかも知れません。しかし、実際に働いている側からみると、集計された数値と医療現場の実態とのギャップを感じざるを得ない報告だと思います。
1-②職場選びのポイント
長時間労働が常態化しているか否かは、実際に働いてみない限りはっきりとはわかりません。
しかし、職場に以下の制度が整備されていて、実際に運用が進んでいるかどうかをチェックすることでも、判断できるかも知れません。
- 業務全般の効率化が進んでいるか?
- タスクシフティングが進んでいるか?
- ICTの活用が進んでいるか?
- 勤務間インターバル制度が導入されているか?
2.休みが取りづらい職場
2-①やめた方がいい理由
休みが取りづらい職場は、あなたのワークライフバランスを崩し、心身の健康を損なう可能性があります。
実際に自分が休みたいときに休みを取りたくても、人手不足と周りの同僚・先輩との兼ね合いで、希望通り休めず悩んでいる看護師は少なくありません。
勤務が連続してくると、頭と体の疲労が蓄積して、業務効率は当然低下しますし、時間内での終業が難しくなり長時間労働になりがちです。長時間労働の常態化による弊害は、前述したとおりです。
日本看護協会「2024年 病院看護実態調査 報告書」によると、2023年度の正規雇用看護職員の年次有給休暇の取得率は、以下のとおりとなりました。
- 90%以上 16.0%
- 80~90%未満 18.6%
- 70~80%未満 18.2%
- 60~70%未満 15.9%
- 50~60%未満 12.9%
- 40~50%未満 7.5%
- 30~40%未満 4.0%
- 20~30%未満 1.6%
- 10~20%未満 2.0%
- 10%未満 0.6%
- 無回答・不明 2.8%
- 平均 69.7%(前年度:67.7%)
日本看護協会 2024年病院看護実態調査報告書 より引用し筆者まとめ
上の資料によると、年休取得率「80~90%未満」が18.6%で、最も多い層になりました。
全体の取得率の平均は69.7%と、付与日数の約7割を年休取得できている計算になります。昨年度の全体の平均は67.7%でしたので、それより2ポイント上昇しています。
年休については、報告書上は比較的取得できているように見えます。問題は取るタイミングなのかも知れません。
週休などの定例の休みについても、年休についても、いかに自分のタイミングで取りやすい環境にあるかどうかが職場選びの重要項目になります。
2-②職場選びのポイント
休みの希望が通るかどうかは、所属長や部署の状況によって違うでしょう。
しかし、職場に以下の取組や運用が進んでいるかどうかをチェックすることで、判断できるかも知れません。
- 有給休暇取得促進を制度化しているか?
- 人員配置が適正化されているか?
- ワークライフバランスに対する意識改革が進んでいるか?
以下の記事では、看護師にとってどのような職場が働きやすい職場なのか詳しく解説しています。併せてご参考ください。
3.ハラスメントが横行している職場

3-①やめた方がいい理由
ハラスメントが横行している職場は、あなたのメンタルヘルスを悪化させ、心身の障害から休職や離職の可能性を高めます。
そもそもハラスメントが横行する職場は、ガバナンス機能が弱いため、職場の雰囲気が悪く、離職率が高くなる傾向にあります。
常に人手が足りませんので、長時間労働が常態化し休みも取りづらく、職場の雰囲気が悪化しまた人が辞めていく…といった、負の連鎖に陥るケースが多いです。
以下、厚生労働省がまとめている労災補償状況から、具体的な障害の要因と労災請求件数の多い職種をまとめました。
- 2024年度の精神障害労災補償支給決定で多くみられた具体的な障害の要因(全職種)
-
- 1位 上司等からパワハラを受けた 224件
- 2位 仕事内容・仕事量の大きな変化 119件
- 3位 顧客等から著しい迷惑行為を受けた108件
- 2024年度における精神障害の労災請求件数の多い職種
-
- 1位 一般事務従事者 577件(うち支給決定 97件)
- 2位 保健師,助産師,看護師 242件(うち支給決定 70件)
- 3位 商品販売従事者 232件(うち支給決定 42件)
資料のとおり、精神障害の具体的な労災の決定要因で最も多いのが、「上司等からパワハラ」です。
そして、数多くある職種の中、精神障害の労災請求件数が2番目に多いのが「保健師,助産師,看護師」などの看護職となっています。
自身の職場を振り返ってみて、あなたの目にはこの資料の数字はどのように写りますか?
3-②職場選びのポイント
様々な状況が起因していると思いますが、上の資料をみても、医療機関はハラスメントがおきやすい職場環境と言えるのかも知れません。
しかし、ハラスメントを許さない職場環境づくりが進んでいるかどうか、以下のポイントをチェックすることでも判断できるでしょう。
- ハラスメント防止の方針が明確化されているか?
- 公正、中立なハラスメント相談窓口が設置されているか?
- 定期的に全職員向けのハラスメント研修が実施されているか?
4.教育・研修体制が整っていない職場
4-①やめた方がいい理由
教育・研修体制が整っていない職場は、スキルアップの機会が少ないため、看護技術の習得に時間がかかり、経験年数に応じた安全な看護の提供が困難になる可能性があります。
不安や悩みを抱えながら看護を提供していると、患者さんとの信頼関係を築くのも難しくなり、看護師としての自信を失います。仕事を続けることが辛くなり、あなたの看護師としてのキャリア形成に影響を及ぼします。
以下、日本看護協会「2023年 病院看護実態調査 報告書」から、「新人看護職員の育成のために教育・訓練の面で強化または工夫して実施したこと(複数回答・病床規模別)」の回答結果を紹介します。
| 病床数 | 技術演習 | 検査や処置の独り立ちまでの技術チェック | シャドーイング | 看護基礎教育機関が行う体験学習等の研修 | e-ラーニング |
| ~99 | 24.3% | 26.6% | 16.1% | 5.8% | 17.2% |
| 100~199 | 49.5% | 45.5% | 35.9% | 10.7% | 38.2% |
| 200~299 | 57.0% | 48.8% | 44.8% | 12.2% | 47.8% |
| 300~399 | 65.7% | 54.4% | 55.2% | 14.5% | 47.7% |
| 400~499 | 71.3% | 56.1% | 61.0% | 13.5% | 61.0% |
| 500~ | 75.1% | 53.7% | 65.3% | 16.5% | 59.3% |
| 計 | 48.6% | 43.0% | 37.4% | 10.6% | 37.8% |
上の資料を見ると、病床規模の大きさで研修制度が充実しているかどうかの傾向がわかります。
つまり、病床規模が大きい程、新人看護師に対する各種研修体制が整備されていることが、数字から読み取れるということです。
「シャドーイング」を例に見てみると、99床以下ではわずか16.1%の実施ですが、500床以上では65.3%実施されており、病床規模による格差の大きさを示しています。
4-②職場選びのポイント
上の資料からは、病床規模によって教育体制が整備されているか否かが判断できます。
病床規模に加え、以下のポイントをチェックすることで、継続的な学習環境の整備が進んでいる職場かどうか判断できるかも知れません。
- 体系的な教育プログラムが導入されているか?
- 外部研修への積極的な参加支援があるか?
- メンター制度があり、活用されているか?
なお、仕事についていけず看護師に向いてないかも…、と適正に悩んだときにどのような対処をすべきか、以下の記事で解説していますので是非ご参考ください。
5.チームワークや人間関係が良好でない職場

5-①やめた方がいい理由
チームワークや人間関係が良好でない職場は、業務を進めるうえで必要な職員間もしくは職種間の情報共有が不足したり、協力体制が欠如します。
情報共有や協力体制の欠如により、医療現場はストレスを抱え、インシデントや実際の医療事故を発生させるリスクを増やします。医療の質、看護の質が低下し、患者さんの命や健康に影響を及ぼします。
前掲した「看護師本人が明かす前職の退職理由」と併せて、次のアンケート結果をご覧ください。
Q.(退職理由が)改善された内容について、当てはまるものをすべて選んでください。
という質問に対し、退職を取りやめた看護師たちはこのように回答しています。
| 退職を取りやめた理由 | ||
| 1位 | 人間関係が改善された | 41.9% |
| 2位 | 勤務時間や休日などの労働条件が改善された | 36.1% |
| 3位 | 異動ができてやりたい仕事ができる環境になった | 24.5% |
| 4位 | 給与が改善された | 22.0% |
一度退職を決意した看護師が退職を取りやめた理由として、「人間関係が改善された」が最も多い回答となりました。
前掲した「前職を退職した理由」のアンケートでも、「人間関係への不満」が1位でした。
このことからも、いかに職場の人間関係が看護師の就業継続上のカギを握っているかが理解できます。
なお、「異動ができてやりたい仕事ができる環境になった」という意見が3位に入っています。「異動」という選択肢は、キャリア形成の面からも、また人間関係の面からも退職を取りやめるきっかけとなり得ます。
以下の記事で、異動か転職か悩んだときに考えるべきポイントについて解説していますので、併せてお読みください。
5-②職場選びのポイント
職場の人間関係は、あなたが心身ともに健康的に働いていくうえで、とても大切な条件になります。
以下のポイントをチェックすることで、良好な人間関係の構築に努めている職場かどうか判断できるかも知れません。
- 定期的にチームビルディング活動を行っているか?
- オープンなコミュニケーション文化の醸成が図られているか?
- スタッフの心理的安全性が重視されているか?
- 多職種連携が強化されているか?
6.患者の安全や医療の質が軽視されている職場
6-①やめた方がいい理由
患者の安全や医療の質、看護の質が軽視されている職場は、常に医療事故のリスクがはらんでいるため必ず避けなければなりません。
このような職場は、あなたが看護師として安全に、安心して働くことができない職場環境と言えます。
安全・安心に看護を提供できない環境では、患者満足度は低下、職業倫理の問題にも発展し、看護師として継続して働いていくうえでの障害となる可能性が高まります。
以下、公益財団法人日本医療機能評価機構がまとめた2022年度「患者満足度・職員やりがい度 活用支援プログラム【年報】」から、「医療介護の質」における「職員やりがい度」の職種別の結果を紹介します。
| 「医療介護の質」における「職員やりがい度」(5点満点) | |
| 全体 | 3.1 |
| 医師 | 3.6 |
| 看護師 | 2.9 |
| 薬剤師 | 3.1 |
| セラピスト | 3.3 |
| 介護職員 | 3.2 |
| コメディカル | 3.3 |
| 事務 | 2.8 |
| その他 | 3.1 |
「医療介護の質」における「職員やりがい度」は、事務を除く医療職種のうち、看護師が最も低い2.9点となりました。
医療や看護の質の部分で、いかに不安や不満を抱えながら仕事を進めざるを得ない環境にあるかがわかります。
引用:公益財団法人日本医療機能評価機構ホームページ・2022年度「患者満足度・職員やりがい度 活用支援プログラム(年報)manzokudo_nenpo_2022.pdf
6-②職場選びのポイント
医療・看護の質や患者の安全を重視する職場環境は、あなたが看護師として安全に、安心して働くための非常に重要な条件です。
以下のポイントをチェックすることで、安全で質の高い医療提供を目指す職場かどうか判断できるかも知れません。
- 安全管理体制を構築し、強化されているか?
- 医療・看護の質改善活動が推進されているか?
- 患者ファーストの医療文化が醸成されているか?
なお、看護師としてのやりがい・働きがいがある職場の特徴や、働きがいを高める方法について、以下の記事で詳しく解説しています。併せてご参考ください。
まとめ
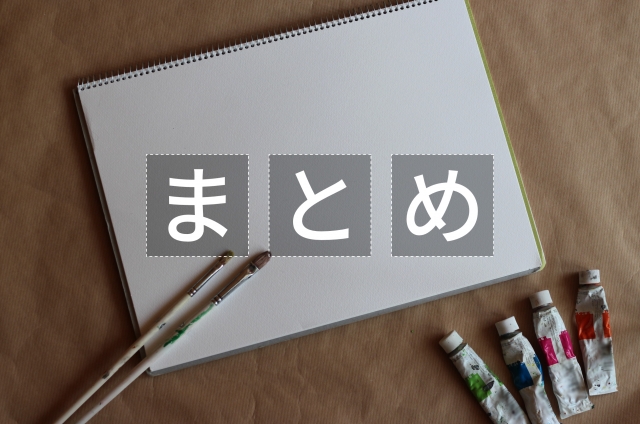
本記事では、看護師がやめた方がいい職場の特徴と、今後の就職先選びのポイントについて解説してきました。
最後に、表にまとめたいと思います。
| やめた方がいい職場 | 職場選びのポイント |
| 1.長時間労働が常態化している職場 | 業務全般の効率化が進んでいるか? タスクシフティングが進んでいるか? ICTの活用が進んでいるか? 勤務間インターバル制度が導入されているか? |
| 2.休みが取りづらい職場 | 有給休暇取得促進を制度化しているか? 人員配置が適正化されているか? ワークライフバランスに対する意識改革が進んでいるか? |
| 3.ハラスメントが横行している職場 | ハラスメント防止の方針が明確化されているか? 公正、中立なハラスメント相談窓口が設置されているか? 定期的に全職員向けのハラスメント研修が実施されているか? |
| 4.教育・研修体制が整っていない職場 | 体系的な教育プログラムが導入されているか? 外部研修への積極的な参加支援があるか? メンター制度があり、活用されているか? |
| 5.チームワークや人間関係が良好でない職場 | 定期的にチームビルディング活動を行っているか? オープンなコミュニケーション文化の醸成が図られているか? スタッフの心理的安全性が重視されているか? 多職種連携が強化されているか? |
| 6.患者の安全や医療の質が軽視されている職場 | 安全管理体制を構築し、強化されているか? 医療・看護の質改善活動が推進されているか? 患者ファーストの医療文化が醸成されているか? |
上記を参考に、看護師として長く働いていくために、理想とする職場環境について考えてみてはいかがでしょうか。
それと併せて、あなた自身の特性や仕事に対する価値観を深堀し、キャリア形成を考えていくうえで絶対に譲りたくない条件などを見返してみるきっかけになれば幸いです。
最後までお読みいただき、誠にありがとうございました。