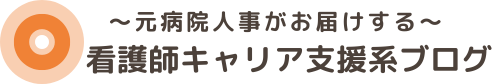看護師転職サイトは本当に使うべきなのでしょうか。
「やめた方がいいって聞いた」
「紹介料で不利になるのでは?」
と不安になる一方で、「一人で転職活動を進めるのは不安」という声も多く聞きます。
筆者は元病院人事として、紹介会社経由の採用にも、直接応募にも数多く関わってきました。
その経験から言えるのは、転職サイトは“良い・悪い”ではなく“向き・不向き”で判断すべきものだということです。
この記事では、
- 看護師転職サイトは本当に必要か?
- 使わない方がいいケース
- 使った方がいい人の特徴
を整理したうえで、主要3社の特徴も比較します。
まずは「そもそも転職サイトとは何か」から確認していきましょう。
看護師転職サイトは本当に必要?まず知っておきたい基本
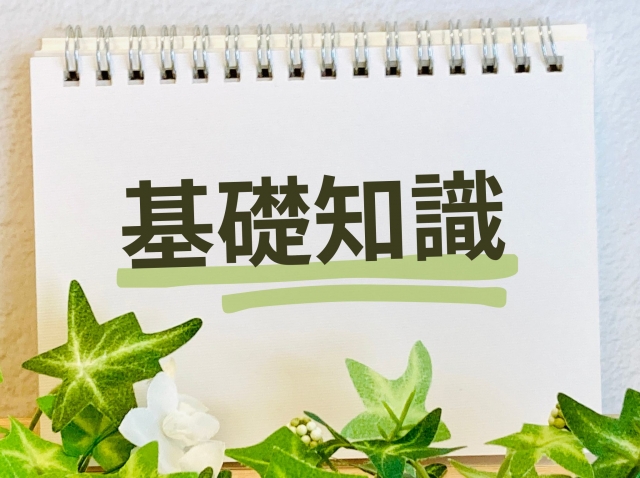
看護師転職サイトとは、求人紹介や面接日程調整、条件交渉などを代行してくれるサービスです。
登録は無料で、紹介が成立した場合に医療機関側がサイト運営会社に紹介手数料を支払う仕組みになっています。
そのため、
- 求職者は無料で利用できる
- 担当者が求人を紹介してくれる
- 内部情報を教えてもらえることもある
といったメリットがあります。
一方で、
- 担当者との相性に左右される
- 紹介求人が中心になる
- スピード感を求められることがある
という側面もあります。
ここで大切なのは、「転職サイトが良いか悪いか」ではなく、自分の状況に合っているかどうかに意識を向けることです。
たとえば、
- 今すぐ辞めたいのか
- 情報収集だけしたいのか
- 条件交渉に不安があるのか
によって、選ぶべき手段は変わります。
次の章では、まず「転職サイトを使わない方がいいケース」から整理していきます。
看護師転職サイトを「使わない方がいい」ケースとは?

「転職サイトはやめた方がいい」という意見を耳にすることがあります。
実際、状況によっては無理に使う必要がないケースもあります。
ここでは、元病院人事の視点から「使わなくてもよいケース」を整理します。
①すでに志望先が明確に決まっている場合
「この病院に直接応募したい」とはっきり決まっている場合は、あえて転職サイトを経由する必要はありません。
特に、
- 地元のクリニックなど小規模施設
- 施設の公式サイトで直接募集している場合
は、直接応募の方がスムーズなこともあります。
②自分のペースでゆっくり情報収集したい場合
転職サイトに登録すると、担当者から連絡が入ります。
それ自体は悪いことではありませんが、
- まだ転職するか決めていない
- 情報収集だけしたい
- 急かされるのが苦手
という方には、負担に感じることがあります。
その場合は、まずは自分で求人サイトを見る、知人に話を聞くなど、静かに情報収集することから始めてもよいでしょう。
③転職理由がまだ整理できていない場合
最も注意したいのがこのケースです。
「なんとなく辞めたい」
「今の職場がしんどい」
という状態で登録すると、気持ちの整理がつかないまま話が進んでしまい、後から後悔することにつながりやすいです。
転職サイトは“決断を後押しする仕組み”であって、決断そのものを代わりにしてくれるものではありません。
まずは、
- 本当に転職すべきなのか
- 何がつらいのか
- 何を変えたいのか
を整理してから利用する方が、納得感のある転職につながります。
まとめ:転職サイトは「万能」ではない
転職サイトは便利な仕組みですが、すべての人にとって最適な選択肢とは限りません。
大切なのは、
「今の自分にとって必要かどうか」
を冷静に判断することです。
次の章では、反対に「転職サイトを使った方がいい人の特徴」を整理していきます。
看護師転職サイトを「使った方がいい」人の特徴

一方で、転職サイトをうまく活用した方がいいケースもあります。
ここでは、利用を前向きに検討してよいケースを整理します。
①自分に合う職場の基準がまだ曖昧な人
「今の職場は合わない気がする」
「でも何が合わないのか分からない」
こうした状態の方は、客観的な視点を入れることで整理が進みます。
転職サイトの担当者は、
- 病院の内部情報
- 職場の雰囲気
- 離職率や残業傾向
などを把握している場合があります。
自分だけで考えるよりも、選択肢を広げながら比較できるのが大きなメリットです。
②今の職場では得られない情報が欲しい人
施設の公式サイトや求人票だけでは、
- 実際の残業時間
- 人間関係の傾向
- 中途採用者の定着率
といったリアルな情報は見えにくいものです。
転職サイト経由であれば、担当者を通して確認できる場合があります。
「失敗したくない」と考える人にとっては、第三者経由で情報を得る価値は大きいでしょう。
③忙しくて転職活動に時間をかけられない人
急性期で勤務している方や、夜勤が多い方にとって、転職活動は想像以上に負担になります。
転職サイトを活用すれば、
- 求人の絞り込み
- 面接の日程調整
- 条件交渉
などを代行してもらえます。
特に、働きながら転職活動をする人にとっては、時間の節約という意味でも大きなメリットがあります。
④条件交渉に不安がある人
人事の経験上、入職後、職場の雰囲気に慣れてきた頃にようやく本当の希望条件が判明することもあります。
給与や勤務条件の交渉を入職前に個人で行うというのは、心理的ハードルがとても高いものです。
転職サイトを通すことで、間に第三者が入る安心感があります。
自ら条件交渉するのに不安や抵抗がある人にとっては、心理的メリットになるでしょう。
まとめ:使うかどうかは「状況次第」
転職サイトは、
- 向いていない人もいる
- しかし、強力な味方になる人もいる
という“道具(ツール)”です。
大切なのは、
「自分の今の状況に合っているか」
を基準に判断することです。
次の章では、元病院人事の視点で“3社の違い”をどう見るかを整理します。
看護師転職サイト3社の特徴を比較(看護roo!・ナース専科・レバウェル看護)

ここまでで整理した通り、転職サイトは「使うかどうか」だけでなく、どう選ぶかも重要です。
ここでは、代表的な3社について、元病院人事の視点で“違い”を整理します。
※順位づけではありません。目的に応じた使い分けの視点です。
①看護roo!|サポート体制を重視したい人向け
看護roo!は、サポートの丁寧さに定評があります。
- 担当者との面談が比較的丁寧
- 職場情報の共有が細かい傾向
- 初めての転職でも安心感がある
- 「転職が初めて」
- 「一人で進めるのが不安」
という方には相性が良いケースが多い印象です。
一方で、スピード感を求める人には少し慎重に感じることもあります。
②ナース専科 転職|情報収集から始めたい人向け
ナース専科は、情報コンテンツが充実しています。
- コラムや体験談が豊富
- 職場の口コミ情報が比較的見やすい
- まずは比較検討したい人向け
- 「すぐに応募するわけではない」
- 「まずは相場や情報を知りたい」
という段階の方にとって、入りやすいサービスです。
一方で、自分で比較・判断する比重がやや高いため、手厚い個別サポートを求める人には物足りなく感じることもあります。
③レバウェル看護|求人数を重視したい人向け
レバウェル看護は、求人数の多さが強みの一つです。
- 幅広いエリアに対応
- 選択肢を多く提示してくれる傾向
- 条件別で比較しやすい
- 「できるだけ多くの求人を見たい」
- 「選択肢を広げてから決めたい」
という方に向いています。
ただし、紹介数が多い分、自分の基準が曖昧だと迷いやすくなる点には注意が必要です。
比較のポイントは「自分の目的」
3社とも無料で利用できますが、大切なのは
“どれが一番か?”ではなく“どれが自分に合うか?”です。
選ぶ際は、
- サポート重視か
- 情報収集重視か
- 求人数重視か
という観点で考えると、整理しやすくなります。
使うと決めた方へ
転職サイトは複数登録も可能です。
ただし、登録しすぎると連絡が増え、負担に感じることもあります。
まずは1〜2社に絞り、担当者との相性を見ながら判断するのがおすすめです。
| 看護roo! | ナース専科 転職 | レバウェル看護 | |
| 特徴 | 丁寧に整理しながら提案 | 情報比較しやすい | 求人数多め・提案型 |
| 向いている人 | 初転職・慎重派 | 情報収集段階 | 選択肢を広げたい |
元病院人事の結論|転職サイトは「使い方」で決まる
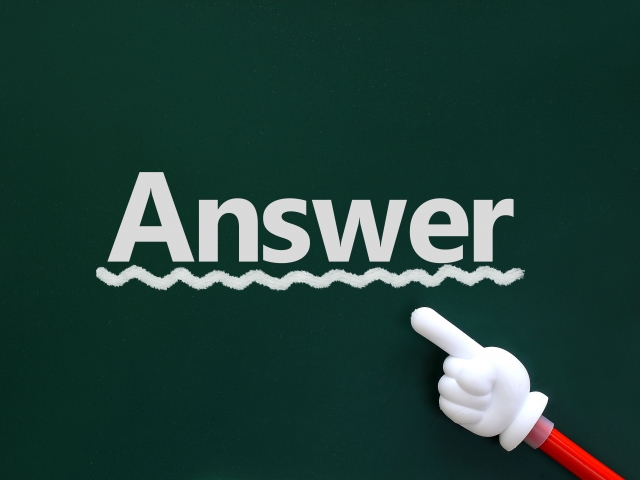
看護師転職サイトは、「使うべき?/やめた方がいい?」という単純な話ではありません。
転職サイトは「人生を決めるもの」ではなく、あくまでも「あなたの判断を支える道具(ツール)」だからです。
大切なのは「順番」
転職活動には順番があります。
- 感情の整理
- 転職すべきかどうかの判断
- 行動(情報収集・応募)
この順番が逆になると、「なんとなく動いた転職」になりやすく、後悔につながることがあります。
転職サイトは「3.行動(情報収集・応募)」の段階で力を発揮します。
しかし「1.感情の整理」や「2.転職すべきかどうかの判断」が曖昧なままだと、選択肢が増える分、迷いも増えてしまいます。
焦って登録しなくていい
「とりあえず登録してみようかな」
そう思うこと自体は悪くありません。
実際、「登録=転職決定」ではありません。
ただし、
- 今はまだ迷いの段階なのか
- すでに動く準備ができているのか
を自分で把握しておくことが重要です。
それでも、必要なときには大きな武器になる
- 忙しくて転職活動の時間が取れない
- 条件交渉が不安
- 内部情報を知りたい
こうした場合、転職サイトはあなたにとって心強い存在になります。
大切なのは、「使うかどうか」ではなく「どう使うか」、です。
迷っている方へ
もし今、「転職するかどうか自体迷っている」状態であれば、まずはこちらの記事から整理してみてください。
▶ 看護師が「転職していいのか迷ったとき」に考えるべき3つの視点
▶ 看護師が「辞めたい」と感じたときに、最初に整理すべき3つの視点
そのうえで、「情報収集を始めよう」と思えた段階で、転職サイトを活用すれば十分です。
情報収集を始めたい方へ
すでに転職を前向きに考えている方は、以下のサービスを比較してみてください。
よくある質問(FAQ)

看護師転職サイトはやめた方がいいのでしょうか?
一概に「やめた方がいい」とは言えません。
転職サイトが向いていないのは、まだ転職するかどうか迷っている段階の方です。
感情が整理できていない状態で登録すると、紹介されるがままに流されてしまい、納得感のない転職につながることがあります。
一方で、条件がある程度明確で、情報収集やサポートを求めている方にとっては、有効な手段になります。
大切なのは「良い・悪い」ではなく、今の自分に必要かどうかで判断することです。
転職サイトを使うと不利になることはありますか?
転職サイトを利用したからといって一概に不利になるとは言えません。
医療機関側は紹介手数料を支払いますが、それは採用活動の一環として想定されているコストだからです。
ただし、担当者との相性や、紹介求人が中心になる点は理解しておく必要があります。
不安な場合は、直接応募と比較しながら検討してもよいでしょう。
看護師転職サイトは複数登録しても問題ありませんか?
複数登録は可能です。
実際に2社程度を併用して比較する方もいます。
ただし、登録しすぎると連絡が増え、負担になることがあります。
まずは1〜2社に絞り、担当者との相性や求人の質を見ながら判断するのがおすすめです。
目的が明確であれば、複数登録も有効な方法です。
直接応募と転職サイトはどちらがおすすめですか?
志望先が明確に決まっている場合は、直接応募でも問題ありません。
一方で、職場を比較したい、内部情報を知りたい、条件交渉が不安という場合は、転職サイトの活用が有効です。
どちらが正解というよりも、
- すでに決めているのか
- これから比較検討したいのか
によって適した方法が変わります。
自分の転職段階に合わせて選ぶことが大切です。